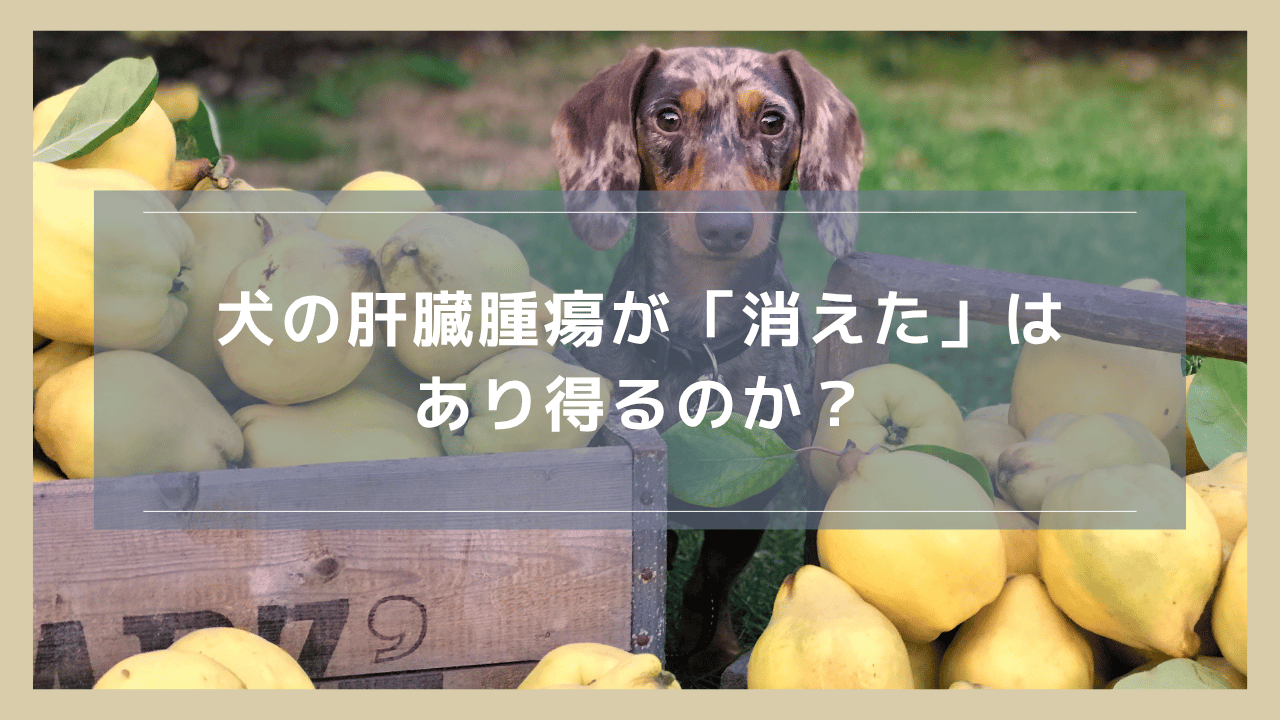肝臓がんになった犬の余命は、がんの発生のしかたによるものの、もっとも多いとされる「肝細胞がん」では手術で大幅な延長が見込めます。
ここでは、肝臓がんになった犬の余命について解説します。
| 犬の肝臓がんは手術で余命延長が見込めるケースが多いものの、まずは正確な診断を行い、手術の適応可否やリスクを見極める必要があります。愛犬の腫瘍に関して不安に思うことがあれば、犬猫の腫瘍にて1000症例を超える治療実績がある当院にご相談ください。 |
腫瘍の疑いがあるなら
治療実績1,000件超え
腫瘍専門医が在籍
上池台動物病院へ
全国6院 お近くの病院を見る
東京都大田区上池台5丁目38−2
神奈川県横浜市南区永田台1−2
静岡県沼津市大岡900−3
愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42
大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104
大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8
この記事の監修者

上野雅祐
上池台動物病院の院長を務める。海外でのセミナーや国際学会、海外大学への短期留学などでジャンルに囚われない幅広いスキルを磨き、外科・腫瘍・皮膚等の専門的で総合的な治療を提供する。
- 監修者情報
-
▼略歴
- 麻布大学 獣医学科卒業(学業成績優秀者)
- 千葉県 中核の動物病院にて勤務医
- 神奈川県 外科認定医・整形専門病院にて勤務医
- 専門病院にて一般外科・整形外科に従事
- 日本小動物がんセンター 研修医
▼所属学会・資格- 日本獣医がん学会
- 日本獣医画像診断学会
- 日本小動物歯科研究会
- 日本獣医麻酔外科学会
- 日本獣医循環器学会
- 日本獣医皮膚科学会
- 獣医腫瘍科認定医Ⅱ種
- ヒルズ栄養学コース修了
- Royal Canin Canine and Feline Clinical Nutrition Course修了
- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル2
- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル4
目次
犬の肝臓がんを治療しなかった場合の余命

犬の肝臓がんでもっとも多いとされる「肝細胞がん」では、手術をしない場合の余命は270日程度と言われています。
※肝細胞がん…肝臓を構成する主要な細胞に由来するがん
肝細胞がんは比較的進行が遅いこともあり、無治療の状態でも半年から1年ほどは大きな症状もなく過ごせることがあります。しかし、その間に腫瘍が成長し肝臓の正常細胞が減ることで、肝機能障害や、胆汁排泄障害による黄疸、胃の圧迫による食欲不振や嘔吐などさまざまな症状が現れます。
無治療の場合、長生きはできないと理解しておくべきでしょう。
犬の肝臓腫瘍(肝臓がん)とはどのような病気か?についてはこちら
高齢犬における肝臓腫瘍の発生リスクについてはこちら
犬の肝臓がんを治療した場合の余命
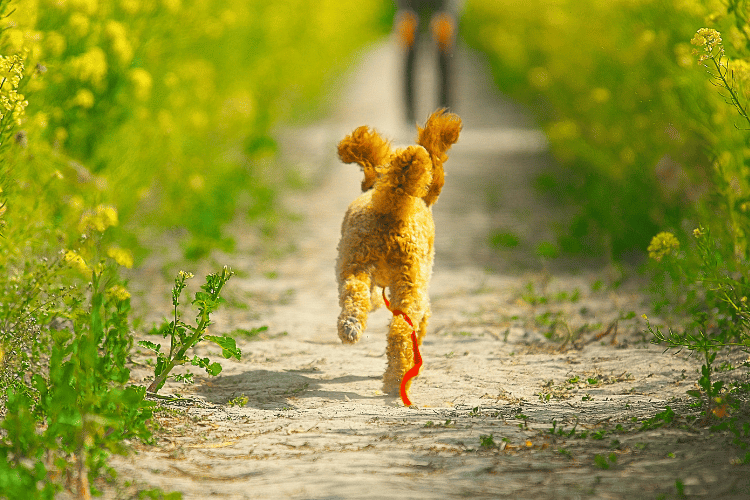
犬の肝臓がんでもっとも多いとされる「肝細胞がん」では、手術により完全切除ができれば生存期間中央値は4〜5年程度となります。肝細胞がんのうち5〜8割は塊状に発生し、転移がなければその部分を切除することで長期の予後が期待できます。
また、不完全な切除であった場合でも、生存期間中央値は2年程度となります。
ただし、これはもっとも多いとされる肝細胞がんのケースです。実際の犬の肝臓がんは発生のしかたにより、小型から中型の腫瘍が複数発生するもの、浸透するように全体に発生するものなどもあります。
たとえば胆管がんは、塊状に発生する割合が3〜4割程度と肝細胞がんより少なく、そのほとんどが術後の再発や転移により半年以内に死亡するとされています。
犬の肝臓がんで生じた腹水は余命に影響を与える?

腫瘍に限らず、肝疾患において腹水貯留は一般的に予後が悪い傾向にあります。
肝臓がんでは、肝機能低下による血中蛋白の合成低下や腫瘍自体の圧迫により、血液が血管から漏れ出やすくなることで起こります。腫瘍による腹水貯留は原因疾患により余命が変化するものの、総じて余命が短くなってしまうといえます。
犬の肝臓がんにおいて「手術=余命の延長」につながるのか?

基本的に、肝臓に発生するがんの多くが肝細胞がんの塊状のものであり、この場合は摘出により格段に寿命が延長するため、「手術=余命の延長」と言えます。
ただし、がんの種類や発生の状況により、ほとんど延命にならない場合も存在します。まずは適切な検査を受け、手術が適応となるかどうかを確認することが大切です。
犬の肝臓腫瘍が「消えた」があり得るのかどうかはこちら
肝臓がんになった犬の余命を少しでも伸ばすには

特に肝細胞がんでは、進行が遅く症状がみられない時期もあるため、定期検診で偶発的に発見されることもあります。症状が出てきたことをきっかけに病院へ行くのは当然のことですが、それ以外では定期的な検診を実施することが重要です。
愛犬が高齢期に入った頃から、血液検査だけでなくX線検査や超音波検査などの画像診断を取り入れていただくことで、早期発見に繋がります。早い段階で診断・治療に進むことができれば手術リスクの低下にもつながるので、定期的な検診を行うようにしましょう。
愛犬の腫瘍に関して不安に思うことがあれば、犬猫の腫瘍にて1000症例を超える治療実績がある当院にご相談ください。当院には腫瘍専門医が在籍しているため、正確な診断と最善の治療提案が可能です。
腫瘍の疑いがあるなら
治療実績1,000件超え
腫瘍専門医が在籍
上池台動物病院へ
全国6院 お近くの病院を見る
東京都大田区上池台5丁目38−2
神奈川県横浜市南区永田台1−2
静岡県沼津市大岡900−3
愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42
大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104
大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8