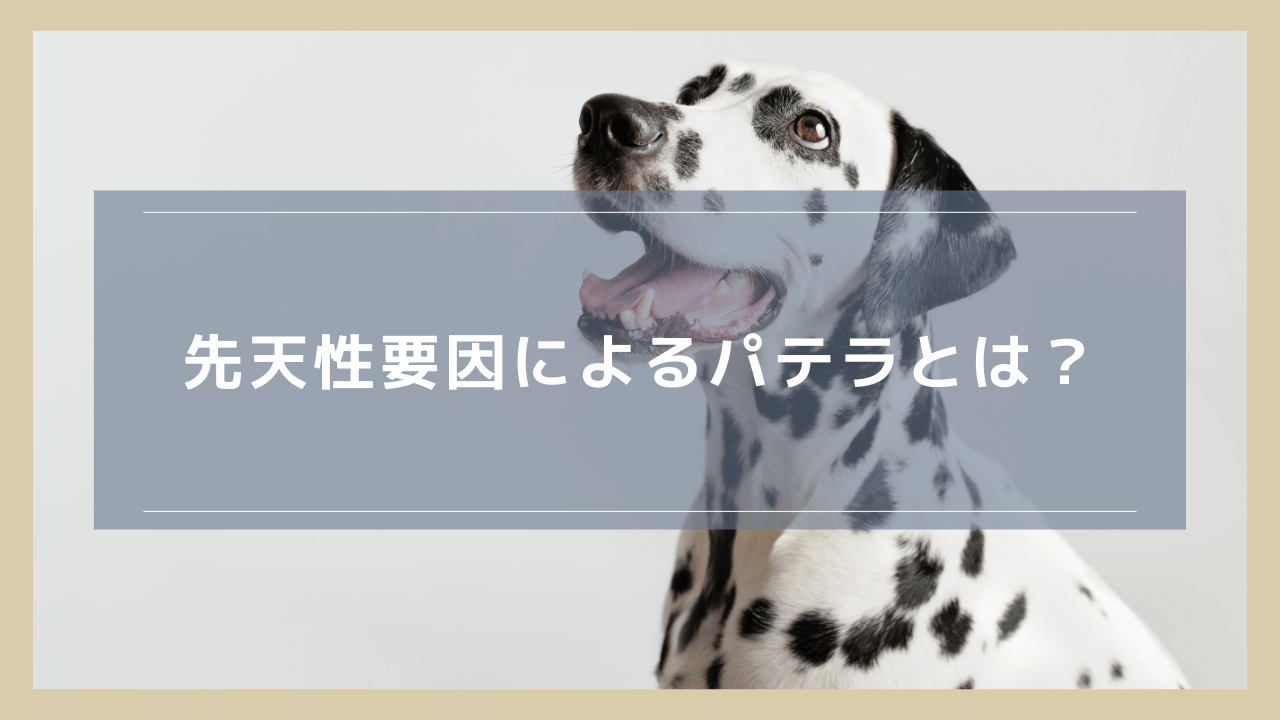犬のパテラ(膝蓋骨脱臼)は、膝蓋骨脱臼の状況により4つの段階に分けられます。グレード判定を参考に治療の種類や治療自体の必要性が判断されるため、パテラにおいてグレードは非常に重要な指標です。
ここでは、犬のパテラのグレード分類について詳しく解説していきます。
| 犬のパテラは、早期に適切な治療ができれば良好な予後が得られます。一方、放置して状態が深刻化すると、手術しても十分な機能回復に至らない可能性もあります。不安に思うことがあれば、整形専門医が在籍する当院にご相談ください。 |
脱臼・骨折・ねんざなどが疑われるなら
整形専門医が在籍
豊富な治療実績
・セカンドオピニオン対応可
上池台動物病院へ
全国6院 お近くの病院を見る
東京都大田区上池台5丁目38−2
神奈川県横浜市南区永田台1−2
静岡県沼津市大岡900−3
愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42
大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104
大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8
この記事の監修者

上野雅祐
上池台動物病院の院長を務める。海外でのセミナーや国際学会、海外大学への短期留学などでジャンルに囚われない幅広いスキルを磨き、外科・腫瘍・皮膚等の専門的で総合的な治療を提供する。
- 監修者情報
-
▼略歴
- 麻布大学 獣医学科卒業(学業成績優秀者)
- 千葉県 中核の動物病院にて勤務医
- 神奈川県 外科認定医・整形専門病院にて勤務医
- 専門病院にて一般外科・整形外科に従事
- 日本小動物がんセンター 研修医
▼所属学会・資格- 日本獣医がん学会
- 日本獣医画像診断学会
- 日本小動物歯科研究会
- 日本獣医麻酔外科学会
- 日本獣医循環器学会
- 日本獣医皮膚科学会
- 獣医腫瘍科認定医Ⅱ種
- ヒルズ栄養学コース修了
- Royal Canin Canine and Feline Clinical Nutrition Course修了
- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル2
- 日本小動物歯科研究会 歯科レベル4
目次
犬のパテラのグレード分類

犬のパテラは、以下のようにグレード分類されます。
| グレード | 状態 |
|---|---|
| グレード1 | 膝蓋骨は脱臼せずに正しい位置にありつつも、手で押すことで脱臼させることができる状態 |
| グレード2 | 膝蓋骨は正常な位置にあるものの、脚の曲げ伸ばしや軽い衝撃などですぐに外れてしまう状態 |
| グレード3 | 膝蓋骨は常に脱臼しており、手で押すことで元の位置に戻せるが、離してしまうとまた脱臼の状態に戻る |
| グレード4 | 膝蓋骨が脱臼した状態から正常の位置に戻すことができない |
基本的に、整復するためには外科手術が必要となりますが、軽度のものであれば保存療法や無治療での経過観察が選択される場合もあります。
それぞれ詳しく解説していきます。
なお、パテラとはどのような病気か網羅的に知りたい方は、以下の記事もあわせて参考にしてください。
犬のパテラとはどのような病気かの詳細はこちら
グレード1
パテラのグレード1は、膝蓋骨は脱臼せずに正しい位置にありつつも、手で押すことで脱臼させることができる状態です。
手で押すことで脱臼しても、手を離すとすぐに正常な位置に戻ります。症状はほとんど認められず、普段気が付かずに生活していることも多いです。
このグレードは基本的に手術適応にはならず、主に体重管理による負荷軽減やサプリメントを用いた補助治療が中心となります。体重の急激な増加や関節炎の悪化等がなければ、正常な子と変わらない生活が送れます。
犬のパテラ「グレード1」は自然に治るのか?についてはこちら
グレード2
パテラのグレード2は、膝蓋骨は正常な位置にあるものの、脚の曲げ伸ばしや軽い衝撃などですぐに外れてしまう状態です。
外れたり戻ったりを繰り返す状況となっており、
- 脚を曲げたときに音がする
- 脚を曲げ伸ばしすることがある
- 脚を伸ばしたまま上げている
など、さまざまな症状がみられるようになります。
膝蓋骨の外れ具合にもよりますが、慢性的に関節炎が進行し、痛みが増してくる可能性があるため注意が必要です。症状の発生頻度が多いなら、手術を実施する場合があります。
内科・外科のいずれの方法でも、早期に症状に合わせた対応ができれば予後は良好です。
犬のパテラ「グレード2」は手術なしで治るのか?についてはこちら
グレード3
パテラのグレード3では、膝蓋骨は常に脱臼しており、手で押すことで元の位置に戻せますが、離してしまうとまた脱臼の状態に戻ります。
グレード3では、それまでの経過から膝の軟骨の損傷が続き、削れ切ってしまうと疼痛が強くなります。脚を曲げたままの状態で歩行するようになるため、骨の変形に拍車がかかるようになります。
このグレードになると内科での管理は難しく、基本的には外科的な整復でしか治すことができません。放置すると関節炎の悪化や骨の変形が進むので、手術が適応となる子については早期の手術が望まれます。
適切な手術の実施ができれば予後は良好であり、合併症リスクも少ないです。
犬のパテラ「グレード3」は手術で完全に治るのか?についてはこちら
グレード4
パテラのグレード4では、膝蓋骨が脱臼した状態から正常の位置に戻すことができなくなります。
この状態だと、骨の変形や筋肉の萎縮、関節炎などが他のグレードより更に進行するため、歩行や姿勢に支障が出るようになります。脚の骨が湾曲してしまうと、普通の状態でO脚やX脚のように曲がっている状態となるため、正しく体重を支えることができなくなり、関節にも強い負担がかかるようになります。
その結果、関節炎も進行していき、より強い痛みを引き起こす可能性があります。
グレード4は手術以外での対応は基本的に不可能ですが、骨の変形が重度な場合や、関節炎の進行が重度である場合には、合併症リスクが高くなるため手術の可否について慎重な判断が必要となります。
他のグレードと比較すると骨や関節への影響が大きいため、適切な手術を実施しても十分な機能回復が見込めない場合があります。
犬のパテラ「グレード4」は手術で完全に治るのか?についてはこちら
脱臼・骨折・ねんざなどが疑われるなら
整形専門医が在籍
豊富な治療実績
・セカンドオピニオン対応可
上池台動物病院へ
全国6院 お近くの病院を見る
東京都大田区上池台5丁目38−2
神奈川県横浜市南区永田台1−2
静岡県沼津市大岡900−3
愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42
大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104
大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8
犬のパテラのグレードを決定するための検査

パテラにおけるグレード評価では、以下のような検査を実施します。
歩行検査
通常時の歩き方から、歩行時の姿勢や脚への体重のかけ方などを確認していきます。院内では緊張で普段通りの動きをしなくなってしまうこともあるので、動画を利用することもあります。
よくみられるパテラの症状としては、次のようなものがあります。
- 歩行時または走ったときに突然脚を上げる
- スキップするような歩き方をする
- 膝から崩れるような歩き方をする
- 脚を上げたままにしている
- 脚をストレッチするように伸ばす
犬が後ろ足を伸ばす動作とパテラの関連についてはこちら
触診
実際に患肢を触ることで、
- 手で膝蓋骨が動かせるか
- 筋肉の左右差はあるのか
- 脱臼状態での力の入り具合はどうか
などを確認していきます。
X線検査
関節炎の有無、骨の変形、筋肉の状態などを確認します。
症状が進行している場合、
- 膝蓋骨と繋がっている大腿四頭筋の萎縮がみらる
- 膝関節が関節炎を起こすことで白く見える
- 関節部分の骨が削れている
などが確認できます。
そのほかに、膝蓋骨が接している部分の大腿骨の溝の深さや、大腿骨の湾曲具合もX線検査にて調べます。
まとめ

犬のパテラは、グレード1なら手術ではなく補助治療が中心となりますが、グレード2以降は状態に応じて手術を検討することになります。ただし、グレード4まで発展してしまうと、合併症リスクを鑑みて手術が難しいという判断になるケースもあります。
いずれにせよ、少しでも予兆が見られた場合は動物病院を受診し、グレードに応じた適切な治療を進めることが大切です。
脱臼・骨折・ねんざなどが疑われるなら
整形専門医が在籍
豊富な治療実績
・セカンドオピニオン対応可
上池台動物病院へ
全国6院 お近くの病院を見る
東京都大田区上池台5丁目38−2
神奈川県横浜市南区永田台1−2
静岡県沼津市大岡900−3
愛知県名古屋市中区大須1丁目35−42
大阪府大阪市港区弁天1丁目4−9 第3柴田ビル 104
大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目19-8